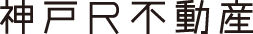第64話 Helter Skelter
2025年 7月
毎日毎日、暑いですね。ここ連日、体温を超える気温。もう、外に出るのも億劫になっていますが、それでも週末は朝から晩までの農作業、がんばってますよ!

2025年5月 田植え完了しました!
政治的なこと、あまり言いたくない性格なので、いつも能天気なブログを書いてる僕ですが、ずっと思ってたこと、書いてみます。
ここ最近、テレビではずっと「令和の米騒動」なんて騒いで、米不足、米価高騰への対策が参院選の争点にもなっていましたね。
・・・米の値段が上がるのは悪なのか?
確かに主食だから価格の安定を望むのは解りますが、物価高騰は米に限ったことではなく、世の中全ての物価が上がっているのに、米の値段は上がってはいけない?
日本は30年続いたデフレを脱却して、やっとインフレ経済となった訳ですから、基本的に物価が上がるのはわかりきっていて、その中でも物価高の象徴のように「米の値段が上がることが悪い」と言われているようで腑に落ちません。生産者としては。
しかも、米価の値上がり分は流通の過程でごっそり抜かれていて、生産者の手取りの増額はせいぜい1~2割ほど。(実感による自分調べ)
「米作っても食えない」
「作れば作るほど借金が増える」
「米農家の時給10円」
↑これ全て農家の本音(価値観)です。
農林水産省の統計「水田作経営の農業経営収支」によれば、主に水田で耕作している農家の平均農業所得は、2021、2022年と2年続けて1万円だそうです。 農業に費やした労働時間の平均は1千時間ほどで、「時給」に換算すると、なんと10円。
10アール(1反)の田んぼで稲作のコスト(平均生産費)は年間約12万8000円。仮に10アールにつき9俵の米(540キロ)が取れたとして、23年の米価平均1俵(60キロ)あたり1万4000円ほどで考えると、農家の手取りは12万6000円。コストが12万8000円なら2000円の赤字です。農家ごとに様々な努力をしてコストを削減した結果の平均農業所得(売上-経費)が年間1万円、それを時給換算すると10円になるわけです。
国はいま、農地の大規模集約化によって農業を持続可能にするため、大規模農家(農業生産法人等)に対して補助金などを手厚くしていますが、農家の大半を占める小規模農家(当然水戸農園もここ)は、例えば年間の所得が下がったときの価格保証制度には入れないとか、補助金の対象外なのです。
そもそも、米農家は減反政策や経営安定化補助金など長年補助金漬けにされ、補助金がなければ成り立たない米作りがいずれ行き詰るのは予想できたことで、そんな農家の大半が70歳を過ぎているので、米作りを続けるのはさらに難しくなるでしょう。もちろん、時給10円なんて商売に後継者はいませんから、あと数年もすれば間違いなく米農家はもっと減っていくはずです。
これが米農家の現実であり、日本の長年の農業政策の結果です。
ただそんな現状の中でも、有機米づくりや既存の流通に頼らず直接消費者へ販売してファンを増やして収益性を高め、国の大規模集約化に合わない中山間部の水田を再生して、小規模でも持続可能な米作りを始めている新規就農者も増え始めています。
本当の「持続可能」って、↑こういうことだよね?
大規模集約化して機械化によって生産効率だけを上げ、機械化に合わない中山間部の農地は切り捨てる、なんて、とても「持続可能」とは思えません。しかも日本の農地の7割が中山間部で、それを小規模でも個々の農家が家族単位で守り、引き継いできたからこそ、今まで何とか維持されてきて、そこには中山間部ならではの、知識とか技術とかコミュニティの協力とか愛情とかが蓄積されてきたはずで、そいいうものが軽視される農業経営なんて信じられますか?持続するんでしょうか?
世界中のどこの国でも、主食を大切に守り増産しているのが当たり前の現実。
主食は国の安全保障にとって防衛力と同じぐらい重要だというのが世界の常識です。
一方、日本では米の消費量は年々減少し、結果、主食である米を減産し続けてきて、今や米不足、価格の高騰、そして食料自給率は40%に満たない・・・。
経済的、物質的には豊かになったのかもしれませんが、農政や食糧問題を自分ごとと捉えていない、危機感のない島国で、それが社会問題になるのは当然ですね。
この米騒動をきっかけに、「主食」について、その「価値」について、一人一人がよく考えて、資源は無くても食料は自前で作れる国になればいいですね。
・・・・・・・・・
5月なかばに田植えを終え、息つく暇なくサクランボのハウスの設営、6月は怒涛の収穫、出荷を終えました。亜熱帯になってしまった今の気候では、天候不順による受粉障害やら高温障害やら、今年もやっぱり不作でした。とほほ。

2025年6月 今年も不作だったけど、できる限りの手をかけ世話をして、サクランボ収穫しました。
そして、水戸農園からのお知らせ
水戸農園の日常の作業の様子を、専業農家の妻がinstagramに投稿してますよ!
@mitonouen(https://www.instagram.com/mitonouen/)
田植え風景やサクランボ作業も動画で見れます。
妻のモチベーションアップのために、いいね♡ よろしくお願いします!
つづく
 このブログについて
このブログについて山形R不動産メンバーの水戸靖宏が、ある日突然兼業農家になり、戸惑い、苦悩し、時折愚痴を言いながらも、楽しく農地と向き合っていくストーリー。後継者不足で増え続ける空き農地。山形R不動産では物件ばかりではなく、農地や農業も紹介してしまうのか!?
 著者紹介
著者紹介水戸靖宏(山形R不動産/千歳不動産・マルアール代表)
山形R不動産の代表であり、千歳不動産株式会社の代表取締役、そして株式会社マルアールの代表も務め、さらに現役の兼業農家として、ラ・フランスやさくらんぼを栽培。


















![[団地を楽しむ教科書] 暮らしと。](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/rincglobal/common/thmb_kurashito_book.png)